読書離れ、本離れ、活字離れ。
教育にとって、そして出版業界にとって大きな問題です。
残念ですが、今後も進んでいくことは避けられないでしょう。
うちの子も、本は読まないのにyoutubeは毎日見ています。
なぜ、本よりも動画の方が好まれるのでしょうか?
ぼくの答えはシンプルです。
「本がつまらないから」
「本よりもyoutubeの方がおもしろいから」。
少し言い方を変えます。
「おもしろい本を知らないから」
「おもしろい本に出会っていないから」。
その原因のひとつが小学校の読書感想文だと思っています。
読書感想文のあり方が、「本はつまらないもの」と教え込んでいるのだと。
今回は、読書感想文の問題点について考えます。
読書感想文対策としてのオススメ本の記事はこちらをご覧ください。

本の種類の指定|絵本や図鑑の禁止
読書感想文のために読む本は、物語(小説)と指定されます。
絵本や図鑑は禁止です。
絵本でも図鑑でも、自分の好きな本を読めれば楽しさを感じることができます。
感じることも多いので、いろんな感想をもつはずです。
でも、それらは禁止され、物語を読むように強要されます。
本当に読みたい本を読ませてもらえず、おもしろいのかどうかさえわからない推薦図書を読まされる。
つまらないので、本当はつまらなかったという感想しかないのに、無理していろいろ書こうとするけど、当然何も思いつかない。
イライラする。貴重な夏休みがどんどん削られていく。
結局、「読書感想文なんて嫌いだ」「本なんてつまらない」となる。
いかがでしょうか?
子どもに小説を読ませる目的が不明確であることが問題だと思います。
将来の仕事のために読ませたいのか。
でも大人が仕事で読む文章のほとんどが、感情の入り混じった小説のような文章ではなく、論理的な法律や契約書のような文章です。
確かに、前後の文脈や言葉になっていない行間を読み取ることが必要な場面もあります。
でもそれは、必ずしも書類上ではなく、会議などの会話の場面でも起こります。
なので、そういった能力を養うのであれば、ドラマを見てもいいわけです。
では、教養として文学作品を読ませたいのか。
でも、文豪の作品は言葉遣いが古いし、時代背景も異なるので、そもそも子どもがとっつきにくい。
じゃあ、絵本版の「論語」ならいいのか、横山光輝の漫画「三国志」ならいいのか、というとたぶんそうではない。
谷川俊太郎の詩をベースにした『生きる』というすばらしい絵本があります。でも、詩人の詩も絵本だからダメなんでしょうね。
なので、小説を指定する理由は、単に「長い文章を読ませたい」ということしかないことになります。
「普段長文を読んでないんだから、夏休みくらい読めよ」ということです。
そして、自分の興味に合わないつまらない本を読まされ、ついには本嫌いになる。
ぼくは本好きな方ですが、それでも、退屈で最後まで読めない本はあります。
川端康成の『雪国』とか。
ページ数の指定
小学校高学年の長男の読書感想文の課題は、200ページ以上の長編小説です。
百歩譲って小説を読むとして、長編を指定されたら、おもしろい作品に出会う確率は限りなくゼロに近づきます。
それに、せっかくのチャンスなのに、名作を読む機会さえ失われてしまいます。
- 太宰治『人間失格』 166ページ(新潮文庫、平成16年151刷)
- 川端康成『雪国』 179ページ(新潮文庫、平成16年128刷)
- 谷崎潤一郎『春琴抄』 106ページ(新潮文庫、平成15年106刷)
- カフカ『変身』 121ページ(新潮文庫、平成9年83刷)
- カミュ『異邦人』 146ページ(新潮文庫、平成15年111刷)
- シェイクスピア『マクベス』 158ページ(新潮文庫、平成元年40刷)
- ベケット『ゴドーを待ちながら』 196ページ(白水社、2006年19刷)
※ページ数には「あとがき、解説、年表等」を含む
文学作品の価値は、文字数に比例しないはずで、短編にも優れた作品がたくさんあります。
いたずらに文学から子どもたちを遠ざけているようにしか思えません。
感想文の検閲
苦労してようやく書いた読書感想文は、最後に先生の検閲を受けます。
文量が足りないとか、この表現はだめだとか、もっとこういうことを書けとか。
そもそも読書感想文という宿題は、本の批評ではなく、本を読んだ感想を書くものです。
何を感じようが読者の勝手なわけで、その内容をとやかくいうのは筋違いだと思います。
長編小説を指定された時点で本嫌いになっているのに、「楽しかった、すばらしかった、感動した」なんて書けるわけがありません。
結局思ってもいないことを書くことになるので、立派な感想文なんてできあがるわけがありません。
だから、「読書感想文=面倒くさい宿題=本はつまらない」ってなってしまうんだと思います。
例えば、今ぼくの手元に安部公房の「R62号の発明」があります。
ピースの又吉さんもオススメしていた本です。
これは、自殺志願者がどうせ死ぬならと勧誘されてロボットに改造される話です。
昭和28年発表の作品で、50ページ程度の短編です。
ぼくは、この短編についてすすんで感想を書くことができます。
たぶん数枚の原稿用紙にまとめる方が難しいです。
きっと、好きな絵本や好きな図鑑を読んだ子どもたちも、同じ反応になるのではないかと思います。
でも、もし嫌いな『雪国』を読まされたとしたら、こんな感じになると思います。
ぼくは、自分の存在、自分の人生について考えさせられる本が好きです。『雪国』は、自分にとってそうではなさそうな気配がしたので、どうしても読み切ることができませんでした。教科書がオススメする名作が自分にとって必ずしも有益ではないことがわかったのでよかったです。以上。
たぶん、これ以上は書けません。
まとめ
読書感想文というのは、子どもが本に親しむチャンスでもあります。
ですが、読書感想文で嫌な思いをし続ける限り、本嫌いな子どもが再生産され続けていくのではないかと思います。
なので、子どもたちが好きなジャンルの本、自発的に読める本をもっと自由に読ませることが、結果的に本離れの解決につながるのではないかと思います。
絵本だって、図鑑だって、マンガだって、短編小説だって、そこから興味が派生すれば、「もっと詳しく知りたい」という気持ちが生まれ、自ずと別の本を手にとるかもしれません。
そのことは、権威が勧めた小説を読むより、よほど価値のあることだと思います。
ぼくが文学に感動したのは20歳の頃です。
だから、
「いつか、いい文学作品に出会えればいいね」
自分が先生なら、こう言ってあげたいなと思います。
課題図書、学校のオススメ、出版社のオススメの本が、すべて自分の興味をひかないということはよくあります。
なので、その中から選ぶと必然的につまらない読書になります。
でも、本は無数にあるので、自分では何を読んでいいのかわからない。
したがって、子ども一人ひとりの興味にピッタリ合う本を紹介できる大人がいれば、文学に楽しみを感じられるかもしれません。

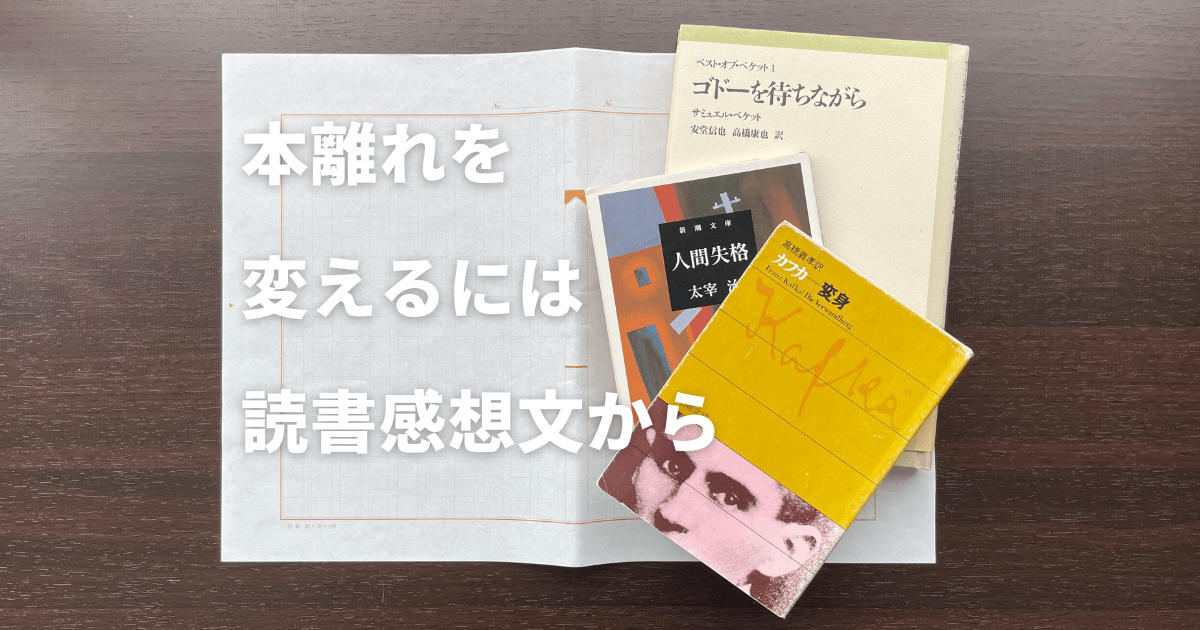
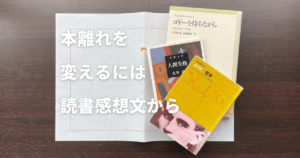
コメント
コメント一覧 (2件)
同じように川端の文章が短い作品なのに読めませんでした。綺麗すぎるし、冗長だし、都会臭くて権威的で。でもこの前、久しぶりに手にとった日焼けした文庫が以外と苦にならずに読めたので、味覚が少し変わったんだと思います。
本は出会いのタイミングが大切です。だから、本好きは親しい人にもあまり本を勧めません。大切な一冊はその人にしか見つけられないことを知っているので。
だから大人は、子供に読書を無理強いするより、たくさん本との出会いの場を与えたほうが生産的だと思います。なんなら授業せずに一日中図書室にほっておいてもいい。そして、絵本もマンガも含めていろんな本に触れさせて、お気に入りの一冊に読書感想文を書かせる。そっちのほうが文章を学ぶ上でも、成長の上でも断然役に立つと思います。
本はタイミングですよね。
これまで苦手だった本が読めるようになったり、逆に好きだった本を手にとることができなかったり。
それは自分自身が変わった、成長したということでもあると思います。
何でもスマホでできる時代にあえて読書を薦めるからには、そういった読書の奥深さまで教えてあげてもいいのではと思います。
本を読むということは、知識を得るだけでなく何かを考えることでもあると思います。
「何を読むか」ではなく「何を考えたか」を大切にすべきだと思っています。