「日本軍の失敗から何を学ぶか」
これが本書のテーマです。
この本は、ぼくが生まれた1984年(昭和59年)に刊行されています。
つまり、約40年前の本だということです。
にもかかわらず、ぼくが受けた衝撃は言葉で表現できるものではありません。
だって、自分が働いていたお役所の体質がそのまま書かれているんですから。
もうすぐ戦後80年、本書刊行40年を迎えるというのに、日本人は失敗から学ばないんだということを身をもって感じました。
今まで読んだビジネス書の中で最も参考になった一冊なので、全体については別の機会に書きたいと思います。
今回は、本書のうち、ミッドウェー作戦での失敗について書いていきたいと思います。
マジでオススメの一冊です。
ただし、実践的なビジネススキルを学びたい人には向いていません。
昭和17年6月5日、日本海軍はミッドウェー島の攻略作戦を実行。
空母艦載機による第1次攻撃として、ミッドウェー島の陸上施設を攻撃。
空母に残った艦載機は、米空母への攻撃のため魚雷を搭載し待機していたが、ミッドウェー島への第1次攻撃の成果が不十分であったこと、偵察で米空母を発見できなかったことから、島陸上施設への第2次攻撃を行うことした。
その際、艦載機の兵装を、艦船を攻撃するための魚雷から、陸上施設を攻撃するための爆弾に切り替えることになった。
しかし、第2次攻撃の準備中に、偵察機より米空母発見の一報が入ったため、攻撃目標をあらためて空母に変更。搭載兵器を爆弾から再度魚雷に切り替えることとなった。(魚雷→爆弾→魚雷と変更)
さらには、第1次攻撃を終え、ミッドウェー島から帰投した部隊を空母に収容しなければならなかった。
その混乱の最中に、米空母艦載機が来襲。
日本軍の空母は、攻撃準備中の航空機を搭載した状態で攻撃を受け、4隻の空母のうち3隻を一挙に喪失。残る1隻も同日中に戦闘不能となった。(同時に多数の航空機と優秀なパイロットも失った)
海戦の主力であった空母を一度に4隻も失い、以後日本軍が戦況を逆転することは不可能となった。
目的の二重性―あいまいな作戦目的
「二重の目的」(dual purpose)。
ぼくがこの本書のなかで最も印象に残っている言葉です。
皮肉にも、アメリカ海軍のニミッツ提督の言葉として紹介されています。
「ミッドウェー島を占領し、米空母も殲滅する。」
一度に達成できるのであれば、それに越したことはありません。
しかし、もし、どちらかしかかなわないのであれば、どちらの目標を優先して達成するべきか。
日本海軍のなかで統一されていなかったことが、作戦失敗の最大の要因とされています。
以下は、日本軍の作戦目的です。
ミッドウェー島を攻略し、ハワイ方面よりする我が本土に対する敵の機動作戦を封止するとともに、攻略時出現することあるべき敵艦隊を撃滅するにあり
P270
これを読むと、「ミッドウェー島の攻略」と「敵艦隊の撃滅」のどちらが優先なのかわかりませんよね。
むしろ、先に記述されているから「島の攻略」の方がメインで、「敵艦隊の撃滅」はサブのように解釈することもできます。
しかし、連合艦隊司令長官の山本五十六の意図は、「敵艦隊の撃滅」にありました。
国力に著しい差のあるアメリカに勝つには短期決戦しかなく、早期に敵空母群を殲滅することで戦局を有利に進めたいという狙いがあったと言われています。
つまり、この作戦の真のねらいは、ミッドウェーの占領そのものではなく、同島の攻略によって米空母群を誘い出し、これに対し主動的に航空決戦を強要し、一挙に捕捉撃滅しようとすることにあった。ところが、この米空母の誘出撃滅作戦の目的と構想を、山本は第一機動部隊の南雲に十分に理解・認識させる努力をしなかった。(中略)したがってミッドウェー攻略が主目的であるかのような形になってしまった。
P101
作戦目的の優先順位が明確でなかった。
言い換えれば、作戦目的が部隊内で正しく認識・共有されていなかった。
だからこそ、不測の事態に際し、適切な判断ができなかったということです。
アメリカ軍の場合
では、日本軍を待ち受けるアメリカ軍はどうだったのか。
そこには、作戦目的に対する明確な違いが見られます。
一方ニミッツは、場合によってはミッドウェーの一時的占領を日本軍に許すようなことがあっても、米機動部隊(空母)の保全の方がより重要であると考えていた。そして、「空母以外のものに攻撃を繰り返すな」と繰り返し注意していたのである。ニミッツは、ハワイでスプルーアンスと住居をともにするなど日常生活レベルにおいても、部下との価値や情報、作戦構想の共有に努めていたといわれる。
P101
とても明快ですよね。
やるべきことが2つあるなかで、優先順位を明確化し、それを共有しています。
当然、米軍には「ミッドウェー島を守りたい」という気持ちもあったでしょう。
しかし、最終的なゴール、つまり「日本との戦争に勝つ」というゴールに結びつく方を、明確に優先しています。
ミッドウェー作戦は、日本側にとっては奇襲でしたが、米軍は暗号の解析により事前に察知していたと言われています。ただ、ドイツとの戦争のため大西洋にも戦力を割いていることや、兵士の練度なども勘案すると、むしろ当時太平洋上では米軍の方が劣勢であったとも言われています。
結局その差が埋まってしまったのも、作戦目的に対する日米両軍の認識の差であったと思います。
ニミッツとスプルーアンスのやりとりが、半藤一利の『山本五十六』(平凡社ライブラリー)に詳しく描かれているのでご紹介します。
要は日本艦隊への果敢な攻撃を督励しながらも、その裏で、貴重な空母部隊を保存することがミッドウェイ島を救うことよりももっと重要である、とニミッツは言い切ったのである。
(中略)
スプルアンス少将は、命令書をゆっくりと読み下すと、落ち着いた口調でいった。
「日本軍がミッドウェイ島を占領しても、長く持ちこたえられません。今度うまくいかなくても、われわれが、あとからゆっくり取り返せばいい、というわけですか」
ニミッツはにっこりとして答えた。
「そのとおりだ。戦況がおもわしくないと思ったら退却したまえ」
P337-338
根拠を共有
ミッドウェー作戦のように、為すべきことが2つある時、どちらを優先するか。
チームが納得して行動するためには、根拠を明確に示して共有することが重要だと思います。
米軍の場合、ミッドウェー島が一時的に占領されてもいいから、日本軍の空母を攻撃することを選びました。
根拠は、日本との戦争に勝つためには、太平洋の制海権が重要であり、海戦の勝敗は航空機とそれを運ぶ空母によって決まると考えていたからです。
そして、日本の空母を倒し制海権を取ることができれば、ミッドウェー島はいずれ取り返すことができると考えていたからです。
空母を倒すには空母が必要。だから戦況が不利になったら、自軍の空母が沈められてしまう前に退却してもいい。
そこまで認識を共有していました。
一方の日本軍。
連合艦隊司令長官の山本五十六も、空母を倒すことを優先に考えていました。
空母を倒すことによって、太平洋上の制海権を確保し、アメリカ国内の士気を下げ、早期講和に持ち込むという短期決戦を構想していたからです。
しかし、その認識は海軍内で共有されていませんでした。(そもそも「海戦の主役は航空機ではなく戦艦だ」という大艦巨砲主義も依然としてはびこっていたそうです)
作戦の目的が共有されていないので、何をすべきかの判断軸がブレる。
このことは、本書において、レイテ海戦や沖縄戦ついても同様に指摘されています。
そういう組織としての基本的な部分が、当時の日本軍に欠けていたということです。
もし、目的が二重になった仕事に取り組むことになったら、優先順位を明確にし、その上でその根拠をチーム内で共有してほしいと思います。
間違っても “dual purpose” のまま取りかかることのないようにしましょう。
まとめ
ミッドウェー島と敵空母、どちらを優先すべきか。
攻守は違えど、日本軍も米軍も同じ選択肢を与えられていました。
米軍は「空母以外には手を出すな」、「空母をたたければ一時的に島が占領状態になっても構わない」と、空母優先を明確に認識していました。
一方の日本軍は、指揮官によってバラバラな状態でした。「米空母はミッドウェー付近に存在しないであろうという先入観(P104)」すらあったと、本書は指摘しています。
仕事において、あれもこれも同時に達成できればそれに越したことはありません。
また、刻々と変化する情勢において、経営トップが何でも直接指揮をとることができれば錯誤は少なくて済むでしょう。
でも、実際にそんなことはほとんどありません。
だからこそ、目的を事前に明確にし共有しておくことで、情勢が変化した時であっても、目的を貫徹するためにどうすればいいか、各部署、各社員が自分たちで判断し、適切に行動することができるようになります。
最後に。
「感染拡大を抑制しながら、経済を回す」
新型コロナが流行り出した頃、ニュースで何度も耳にしました。
できるのであれば、それがいいに決まってますよね。
でも、それができないとしたら。
現状のリソースではどちらかしか達成できないとしたら、どちらを優先すべきか。
認識を統一できなかったためにどちらの目的も達成することができず、結果的に敗戦を決定づける致命傷を負うことになったミッドウェー作戦と、日本政府のコロナ対応が似ているように思ってニュースを見ていました。
きっとこういうことは、みなさんの会社や組織でも、これからも起こると思います。
悲惨な事態に陥る前に、ぜひ一度本書を読んでみていただきたいと思います。
この他にも、人の生死がかかった作戦がその場の「空気」で決まったとか、組織としての日本軍のヤバさが書かれています。
身近な例をもうひとつ。
プロ野球の落合博満さんが中日ドラゴンズの監督時代、日本シリーズで8回まで完全試合をしていた山井投手を9回に降板させ、抑えの岩瀬投手をリリーフとしてマウンドに送ったという采配が話題になりました。
結果的に、岩瀬投手は相手チームを抑え、中日ドラゴンズは日本一になりました。
一方で、「日本シリーズ史上初の完全試合」という偉業を目前とした投手交代には異論もありました。
「チームの日本一」と「山井投手の偉業」という2つの選択肢があった中で、落合監督は日本一を選びました。
プロ野球OBの立場で言えば、多くのファンと同じように、私も山井の完全試合を見たかった。
(中略)
しかし、私はドラゴンズの監督である。
そこで最優先しなければならないのは、「53年ぶりの日本一」という重い扉を開くための最善の策だった。
落合博満 『采配』 P76-77 ダイヤモンド社
非常に悩ましい事柄であっても、「目的」に立ち返れば、やるべきことは意外とシンプルだったりするんだなと思いました。
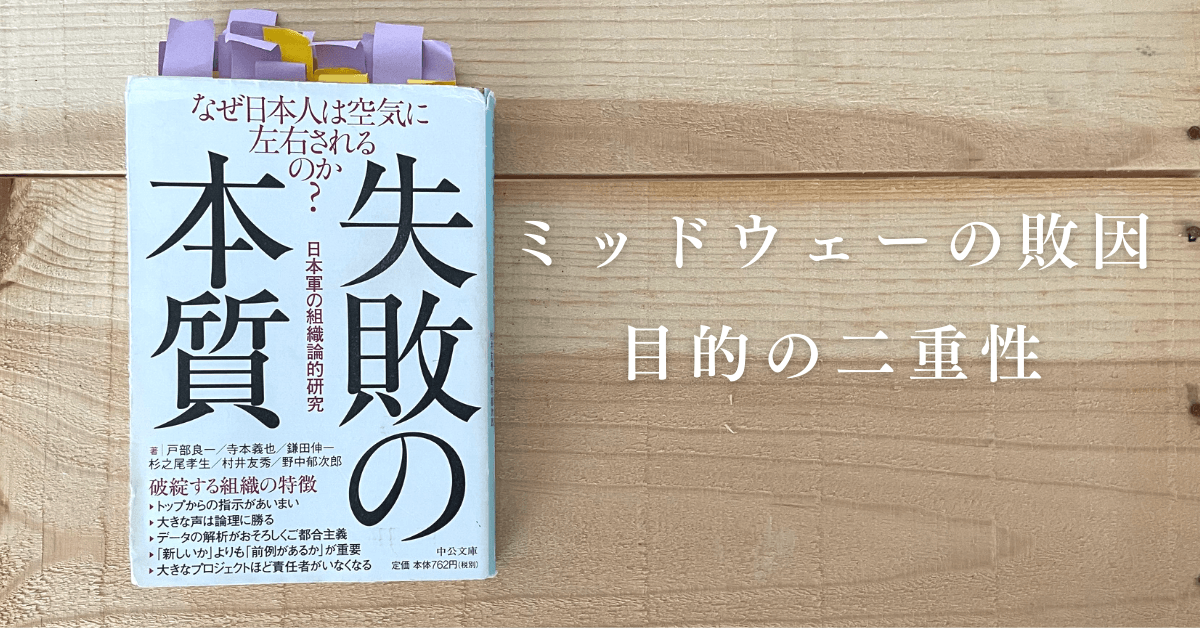



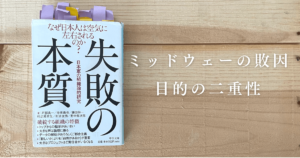
コメント